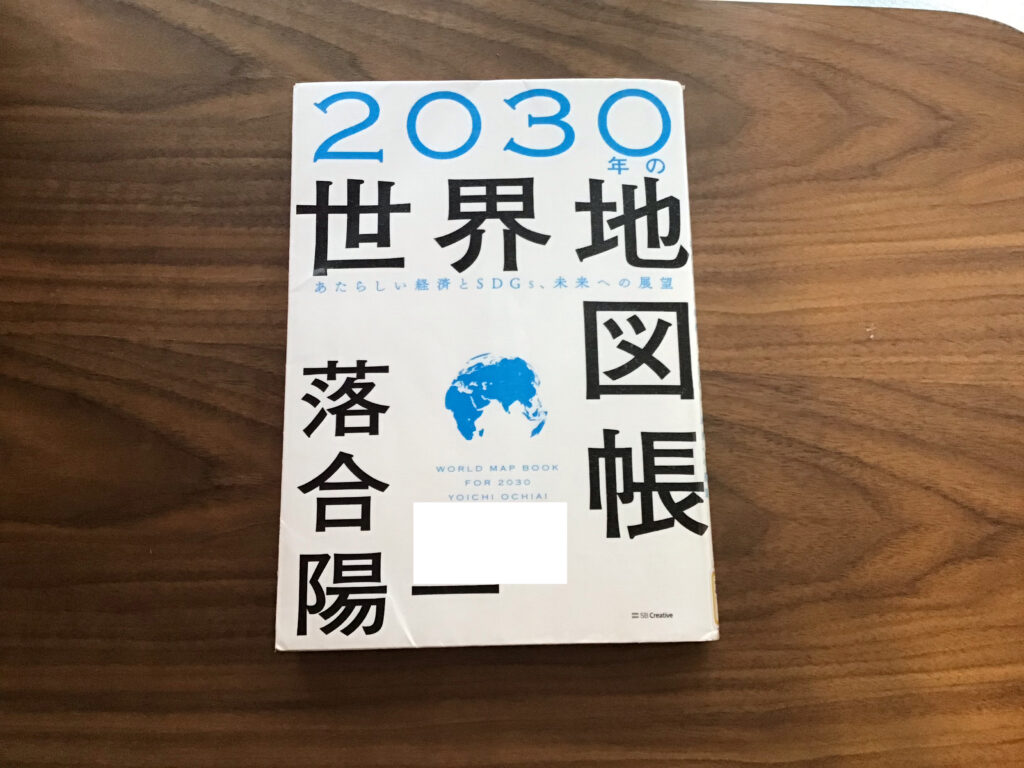

こんにちは。ゆきっぺ(@yukippe_pp)です。
今回は落合陽一さんの「2030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への展望」を要約します。
この本の中には難しい表現もありますが、誰でも理解できるように要約しました!
こんな方におすすめ
- 「2030年の世界地図帳」の要約を見たい
- 世界情勢が不安定で将来に不安を感じている
- これからどのような世界になっていくのか、未来予測を知りたい
目次 [hide]
作者について
この本を書いたのは落合陽一さんです。
今や報道系をメインに多くのテレビ番組に出演されていて、とても有名な方です。
落合さんは1987年生まれ 東京大学大学院卒業。
現在はメディアアーティストとして活躍しながら、筑波大学 図書館情報メディア系准教授、大阪芸術大学 客員教授などを務めています。
東大卒ということもあり、とても知識が豊富な方で、落合さんの本はどれを読んでも一度に沢山の情報を得られます。
本作も経済、歴史、統計学などさまざまなな観点から世界が向かう未来を予測しています。
目次
本作の目次は下記になります。
目次
- はじめに 2030年の世界はどこに向かうのか
- 第一章 2030年の未来と4つのデジタルイデオロギー
- 第二章 「貧困」「格差」は解決できるのか?
- 第三章 地球と人間の関係が変わる時代の「環境」問題
- 第四章 SDGsとヨーロッパの時代
要約
はじめに
この部分では本作の中で、どのようにして未来を予想するかが書かれています。
2000年代にはGAFAM(ガーファム)を始め巨大IT企業が誕生しました。
ポイント
GAFAMはGoogle, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft の頭文字
また、中国が急激に経済発展しアメリカと肩を並べるほどまでに成長。
このような変化の激しい時代には、10年先の予想すら難しいです。
本作ではSDGsや世界のさまざまな統計をもとに2030年の未来を考えるものとなっています。

第一章 2030年の未来と4つのデジタルイデオロギー
ここでは「テクノロジー」と「人口」というテーマから2030年の世界を考えていきます。
テクノロジーといえば、インターネットはネットショッピングやタクシーの配車など、たくさんの革新をもたらしてくれましたね
人口に関しては、中国を見ていると分かるように豊かな人口は経済を大きく活性化させます。
この章で、未来を予測するのにテクノロジー(技術)と人口がいかに重要かが分かりますよ。
また、先進国の中間層の貧困が深刻になっていることも知りました。
つまり、日本のサラリーマンの貧困が深刻になっているというので驚きました。
残念ながら今まで通りの働き方だと、これからは厳しい生活を強いられるかもしれません

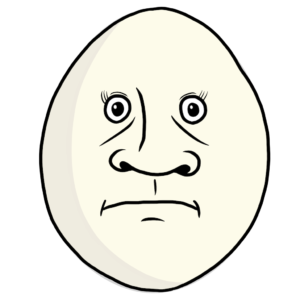
第二章 「貧困」「格差」は解決できるのか?
この章ではアフリカの例を参考に、貧困の解決方法を考えます。
ただ、貧困の解決は本当に難しいものだなと感じました。
アフリカに貧しい国が多いのは過去の西欧諸国による支配や、自ら独裁政権であることが原因です。
独裁政権だと、上級国民だけが潤う仕組みになっているので自ら貧しい国に向かっているようなものですね。
その為、他国が解決を働きかけてもなかなか難しいのが現状です。

特に電子マネー「Mペサ」の普及のおかげで、銀行口座を持たなくてもネット上で送金が出来るようになってきています。
アフリカが進歩してきている一方で、先進国での格差は拡大しています。
その原因は本作の中で確認してみてほしいのですが、日本も貧困は決して遠い国の話ではないということが分かりました。

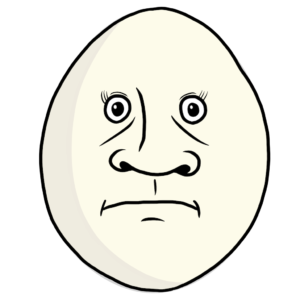
第三章 地球と人間の関係が変わる時代の「環境」問題
ここでは、環境問題はこれまでよりも広い目線で捉えていこう、ということが書かれています。
例えば、日本は水不足とは無縁に思われますが、それは間違っています。
日本が輸入している肥料や食品は、作るのに多くの水が必要です。
国内では消費していなくても、間接的に外国の水資源を大量消費しています。
また、電気自動車がCO2排出をしないと言われていますが、その電気を作るのにCO2がたくさん排出されています。
これからの時代は、表面だけを見るのではなく、背景も見るということを忘れてはいけないと感じました。
第四章 SDGsとヨーロッパの時代
ここではSDGsとヨーロッパの関係性について書かれています。
かなり意外だったのですが、今の価値観はかなりの部分がヨーロッパから来ているのです
基本的人権、民主主義という考え、さらに近代オリンピックはヨーロッパで生まれました。
そういうこともあって、SDGsの考えもヨーロッパの価値観と関係が深いのです。
経済の面で言えば、これからはアメリカのように大量生産・消費したり、中国のように巨大な人口に頼るのではなく、より合理的な市場になっていきます。

実際に読んでみて
この本はまさに未来予想図でした。
これからどのような世界になるのかが分かるので、大学受験を控えている人、就活中の人におすすめです。

